
-
お電話でのお問い合わせ045-285-6015
- ご相談・ご予約
お電話でのお問い合わせ045-285-6015

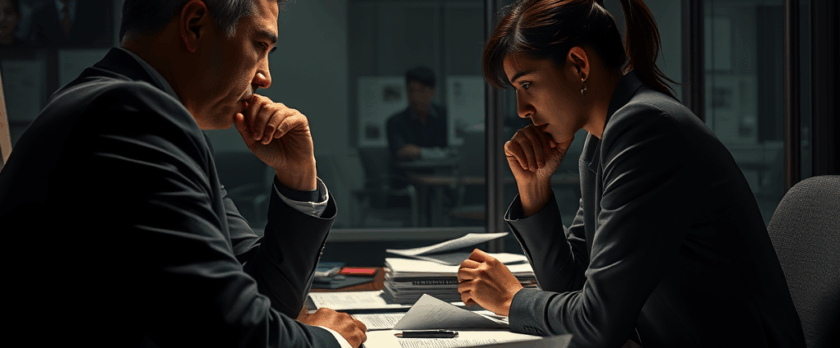
今回は、遺留分侵害額請求について解説します。
被相続人が遺産を相続人または第三者に相続させる遺言をしていた場合、遺産を取得できない相続人が出てしまいます。
しかし、この結論を貫くことは、遺産を取得できない相続人の生活基盤が確保できないことになりかねません。
そこで、特定の相続人の一定範囲の相続分が確保されています。これを遺留分(民法1042条)と言います。
遺留分を有する相続人は、兄弟姉妹以外の相続人です(民法1042条1項)。具体的には、直系尊属、子、配偶者です。直系尊属の遺留分は3分の1で、子・配偶者の遺留分は2分の1です。なお、遺留分を有する相続人が複数いる場合は、法定相続分・代襲相続の規定により、各相続人の遺留分が決まります(民法1042条2項・900条・901条)。
例えば、父親、母親、男子2人の家族で、父親が全財産を母親に相続させる遺言をした場合を考えてみましょう。この場合、長男と次男の遺留分が侵害されていますが、長男と次男の遺留分は、それぞれ、遺産の8分の1になります。
遺留分について重要なことは、期間制限があることです。遺留分侵害額請求は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年を経過した場合、あるいは、相続開始の時から10年を経過した場合は、権利行使することができなくなるので注意して下さい。
特に、検認などで、自己の相続分を侵害する遺言の内容を知った場合は、1年という短い期間内で権利行使する必要があります。
次回も、引き続き、遺留分侵害額請求を取り扱います。